概要
買い付けを入れた土地は一番手をキープしてくれて売買契約の準備が進んでいたのですが、買い付けを入れた土地には複雑な売却事情がありそれに伴うリスクについて記載します。
底借同時売買
買い付けを入れた土地は「底借同時売買」という形になります。
「底借同時売買」とは文字通り底地権と借地権を同時に売りに出して同じ買主に購入してもらうことです。
借地権は割とメジャーですが土地を借りて住宅などを建てられる権利です。
底地権は土地を貸して借地権者から地代を得られる権利です。
| 借地権(借地権者) |
| 底地権(底地権者=地主) |
「底借同時売買」を行うとどうなるかと言うと、底地権者と借地権者がともに私になり、私が自分自身に土地を貸すという状態になります。
その結果、土地賃貸借契約に基づく債権および債務が混同して消滅して単なる所有権の不動産を取得することになります。
| 借地権(借地権者=ヨッシー) |
| 底地権(底地権者=ヨッシー) |
↓
| 所有権 |
買主側としては借地権として買うより所有権として買ったほうが土地の評価は当然高いですし、売主側としても借地権や底地権だけで売却するより高く売れるのでどちらにもメリットはある売買方法となります。
複雑な売却事情によるリスク
売却理由は相続になります。
土地の買い付けを行う10年前に借地権者が新築住宅を建てたのですが、数年後に亡くなってしまい家屋を複数の相続人が相続しました。
そうなると家屋を複数の相続人が持分に応じて使用・収益できるわけですが、相続人同士がほぼ面識がない状況でした。
なぜ相続人同士に面識がないかというと、借地権者の前妻と後妻の関係者が相続人になったり色々と複雑な感じでした。
相続人が複数居るうえに、相続人の1人が認知症になっていて成年後見人の弁護士も絡んでいました。
さらに相続人同士の仲が良くないようで、通常は相続人同士で話をすべきところ全て弁護士を入れて弁護士同士で話を進めていたようです。

相続人の一部が持分を売却することもできると思いますが、弁護士同士で色々と話し合った結果、相続人の総意として借地権を売却しようという話になったみたいです。
また、不動産業者が底地権者にも話をつけて、「底借同時売買」にいたったようです。
(そのほうが高く売れるため)
ところが底地権者に話をつける過程でかなり怒らせてしまったようで、何度も「やっぱり土地は売らない!」と破談になりかけたそうです。

このような感じで借地権者同士も仲が悪く底地権者も結構怒っていて私は全く関係ないのですが土地の売買契約まで無事に進むのか非常に不安でした。
仮に売買契約後に建築業者と請負契約を行っても土地の引き渡しまでに契約解除されてしまったら請負契約も解除せざるを得ないので購入する側としてもリスクがあるなと感じていました。
家屋の内見
私としては土地に買い付けを入れたのですが、実際は築10年の家屋も付いてくるわけです。
解体前提で買い付けを入れているので家屋がどのような状況なのかあまり興味はなかったのですが、それでも築10年の家屋を解体するのは勿体ないので、もし私が希望するRCへの建て替えがうまくいかなかった場合は築10年の家屋を活かして何かを行うことも視野に入れていました。
駅前ですので家屋は住宅と店舗の併用住宅になっていましたが、借地権者が亡くなって以降の店舗は貸しておらず住宅は相続人の1人の親族が住んでいました。
居住中の住宅を内見させていただいたのですが築10年だけあって結構綺麗で正直自分がそのまま住んでもいいかな?と思ったぐらいでした。特に店舗のほうは原状回復工事などは不要でそのままテナント物件として募集できるのではないかと感じました。
ただ家屋の借地権者は投資家ではなかったので土地のポテンシャルを活かした住宅ではなく、高い金額を出して土地を購入するからには建て替え前提でないと採算が合わないのですが、RCへの建て替えがうまくいかなかった場合は壁紙などを張り替えて少しリフォームした築10年の中古物件として売りに出せば間違いなく買い付けを入れた金額以上では売れると感じました。
おまけ
今回は「借地権」「底地権」「混同」「相続人」「成年後見人」「契約解除」などの言葉が出てきましたが、これらは宅建の学習をしていれば理解できる内容ですので宅建業の開業をしなかったとしても宅建の勉強は無駄にはならないと思います。

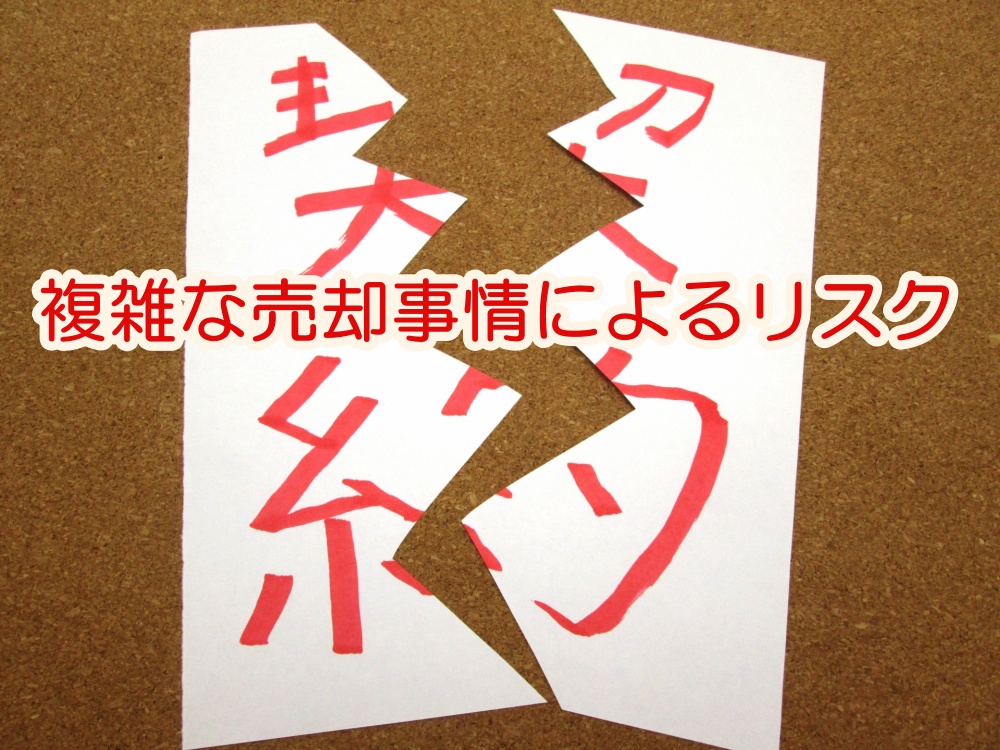


コメント